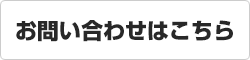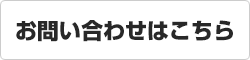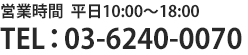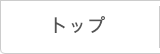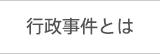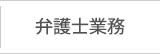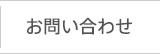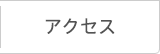預貯金等の使い込みが見つかったら
よく親族に管理を任せていたところ、預貯金等が自分の知らないうちに勝手に引き出されたとか、使い込まれたというようなご相談を受けることがあります。特にご高齢の方は、ご自身での管理に不安があり、任せていた親族や知人、介護者との関係で起きることがあります。それでは、そのような場合にどう対応していったら良いのでしょうか。取るべき対応は次のようになります。
- 事実調査
まずは「いつ」「いくら」「どのように」お金が使われたかを正確に把握します。そのために有用なものとして、以下のものが考えられます。
①預貯金通帳、取引履歴など金銭の動きのわかるもの
②利用に関する領収書、契約書類
- 本人の記憶等の確認
1. で取り寄せたものを確認し、自分が使ったものであるかどうかを確認します。利用した記憶がないとか、依頼した記憶がないものが、まさに「使い込まれた(無断で引き出された)」金銭ということになります。
また、高齢者の場合には、判断能力(認知症の有無、程度など)の確認も必要となります。
これらの調査を踏まえ、自分の心当たりのない利用(使い込み)と思われる場合には、以下の対応が必要となります。
- 詐欺とか窃盗とかの被害と思われる場合 → 警察に相談
- 金融機関等へ今後の使い込み等が起きないように連絡。通帳やキャッシュカード、銀行印などをご自身で管理できるように変更手続をしましょう。
- 民事での被害回収(不当利得返還請求、損害賠償請求)
- 管理者の選任。高齢者の場合、親族による管理等で問題が起きている場合には、第三者(弁護士など)を財産管理人として選任し、財産管理を第三者にしてもらいましょう。
2. で認知症等で判断能力に問題があるような場合には、家庭裁判所に成年後見の申し立てをし、管理をしてもらう第三者として専門家を裁判所に選任してもらいましょう。使い込まれた金員についても後見人等が回収をしていくことになります。
- 高齢者が親族等による使い込み等が判明した場合→親族等による虐待として高齢者虐待として相談。
これらのうち、特にc. の不当利得返還請求や損害賠償請求については、交渉だけでなく、訴訟等によって回収をしなければならない場合も多いです。ですので、法的手続も含めた回収方法については、弁護士に相談することをお勧めします。
さらに詳しいご相談の場合は、
お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
【関連コラム】預貯金等の使い込みの証拠 >>
【関連コラム】金銭使い込みの見つけ方 ー 預金通帳を元に >>
【関連業務】高齢者問題 >>